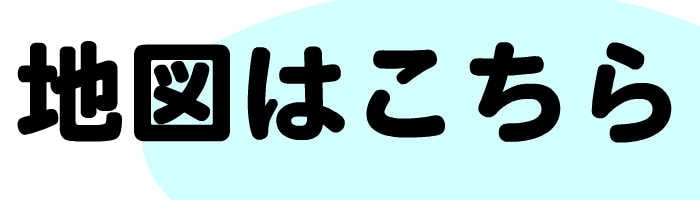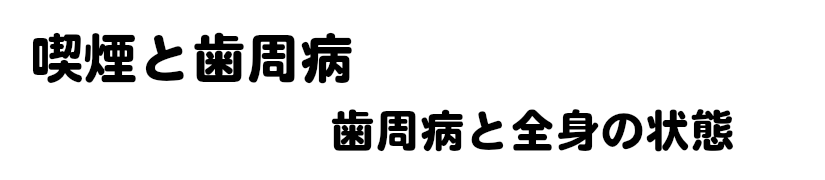
喫煙による歯周病への影響
喫煙は、癌、循環器疾患(心臓病、脳卒中)、呼吸器疾患(肺気腫、喘息)などの多くの病気の原因であることはよく知られています。一方、タバコ煙の入口となる消化器としての口腔、特に、歯肉を含めた歯周組織は、直接、その影響を受けることになります。したがって、歯周病も同じように、喫煙と関連性が強いことは多くの研究により支持され、喫煙は、糖尿病と並んで、歯周病の二大危険因子となっています。
一酸化炭素やニコチンなどによる免疫力、歯茎の血行、白血球の機能、細胞刺激物質産生などへの影響により、歯周組織における抵抗力や治癒に、悪影響が生じます。
その結果、喫煙者では、歯周炎が進行し、そればかりではなく、歯周病の治療への反応や歯周外科手術の経過が不良になることもはっきりしています。これは、日本歯周病学会の分類(2006年)によると、喫煙関連歯周炎と診断されます。
また、受動喫煙によっても、歯肉メラニン色素沈着や歯周病のリスクが高くなることが報告されています。Haniokaら(2005年)の報告では、歯科医院受診者の子どもの歯肉メラニン色素沈着を判定したところ、親の喫煙率は61%で、年齢と性別を補正した子どもの歯肉メラニン色素沈着のオッズ比 (OR)は、それぞれ5.4(95%CI 1.5-20.0)、5.6(95%CI 1.4-21.2)でした。
つまり、親の喫煙が子供の歯肉メラニン色素沈着をおよそ5倍以上のリスクで増強することを報告しています。
さらに、Arbesら(2001年)は、1988-1994年の第3回米国保健栄養調査での5,658名のデータを解析し、家庭や職場で副流煙にさらされている成人非喫煙者(受動喫煙)の歯周病のリスクが57%高くなると警告しています。
禁煙による効果
禁煙により、歯周病を予防し、たとえ進行した歯周炎であっても、歯周治療による治癒がよくなり、歯の喪失が抑えられることも明らかにされてきています。喫煙の歯周組織への影響は、比較的若い年代からあらわれ、しかも発見しやすい部位にあるという点(歯肉メラニン色素沈着、歯の着色、口臭など)が特徴です。しかも、他の臓器に及ぼす影響とは異なり、直接、その影響をご自身でみることができます。